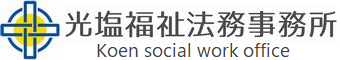遺言執行者による相続登記(支部研修会の補足)
先日の足立支部研修会の折、「相続させる」遺言について遺言執行者は関与できない旨の話をしたところ、会場の方から「今度の民法改正で関与できるようになったのではありませんか」というご指摘をいただきました。
その場でははっきりとした回答ができなかったのですが、確認したところ、会場からの指摘が正しく、私の説明は不正確でした。お詫びを申し上げるとともに、以下のとおり補足説明をいたします。
従来の判例の立場は、例えば「不動産Aを長男Xに相続させる」旨の遺言がなされていた場合、遺言者の死亡(相続開始)と同時にAの所有権はXに移転しているのだから、遺言執行の余地はなく、相続登記はX自らが行うべき(遺言執行者が相続登記をすることはできない)というものでした。
ところが、今般の改正により、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」(1014条2項)という規定が設けられました。
「不動産Aを長男Xに相続させる」旨の遺言は特定財産承継遺言に当たるので、遺言執行者は当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為(=相続登記)をすることができるというわけです。
なお、899条の2も今回の改正で新設された規定で、法定相続分を超えて得た部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない旨を定めています。
法定相続分を超える相続分の指定については、第三者との関わりでは登記・登録などの先後関係によることとなるので、権利関係を早期に安定させる趣旨から遺言執行者の関与を認めることにしたのでしょう。899条の2と1014条2項はワンセットということですね。
そうなると、行政書士が遺言執行者に指定された場合、遺言執行者の立場で特定財産承継遺言について相続登記の申請ができるということになりそうですが、どうなのでしょう‥‥
<令和2年3月19日追記>
1014条2項から4項までの規定は、施行日(令和元年7月1日)前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者による執行については、適用がありません(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則8条2項)。